今回も前回に引き続き、お金に関する記事を書いてみました。
不妊治療を始めるときに多くの方が不安に感じるのが「費用」のことです。
私たちもかなりの不安がありました。
体外受精や顕微授精は1回あたり数十万円かかることも珍しくなく、経済的な負担が大きい治療です。
しかし実は、高額療養費制度を利用することで、医療費の自己負担を大幅に減らすことができます。
今回は、不妊治療における高額療養費制度の仕組みと、実際の使い方、さらに最近増えているマイナンバーカードを保険証として利用した場合の便利な点もあわせて解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、同じ月に支払った医療費が高額になった場合、自己負担の上限を超えた分が払い戻される仕組みです。
例えば、1か月に30万円の医療費がかかっても、実際の自己負担額は「収入に応じた上限額」までに抑えられます。
70歳未満の場合は、収入に応じて次のようになります。
- 年収約370万~770万円の方 → 自己負担は 約8万〜9万円/月
- 年収約770万~1,160万円の方 → 自己負担は 約16万円/月
- 年収約370万円以下の方 → 自己負担は 約5万〜6万円/月
上限を超えた分は、健康保険から払い戻されます。
不妊治療で高額療養費制度は使える?
2022年4月から、体外受精や顕微授精などの「特定不妊治療」が保険適用になりました。
そのため、これらの治療にかかった費用も高額療養費制度の対象になります。
- 体外受精(IVF)
- 顕微授精(ICSI)
- 採卵、受精、胚移植に関する処置
- 入院や投薬にかかる費用
- 保険がきかない自由診療(例:タイムラプス培養法など)
- 自治体の助成金でまかなわれた分
- 差額ベッド代、食事代など
ポイント:保険診療分は高額療養費制度の対象ですが、自由診療は対象外です。
実際にどれくらい安くなる?
例:体外受精1回で40万円かかった場合
- 保険適用(3割負担):約13万円
- 高額療養費制度(年収600万円の方、上限約9万円)
→ 自己負担は約9万円で済むことに。
さらに自治体の助成(例:5万円)があれば、実質4万円の負担になります。
高額療養費制度の使い方
事前に健康保険組合に「限度額適用認定証」を申請しておくと、病院窓口での支払いが最初から上限額で済みます。
一時的に多額の支払いを避けたい人におすすめです。
2021年以降、マイナンバーカードを保険証として登録している人は、限度額適用認定証の提示が不要になる場合があります。
病院窓口でマイナンバーカードをかざすだけで、健康保険組合の情報と自動で連携し、自己負担額が上限までに抑えられる仕組みです。
- 事前の書類申請が不要
- カード1枚で医療費の軽減が可能
- 窓口での支払いがスムーズになる
ただし、すべての病院で完全対応しているわけではないため、通院予定の医療機関に対応状況を確認することが大切です。
限度額適用認定証やマイナンバーカードを利用せず、いったん全額支払っても、後日健康保険組合に申請すれば払い戻しを受けられます。
さらに知っておきたい制度のポイント
同じ世帯の医療費は合算できます。夫婦で同じ月に通院していれば有利です。
1年に3回以上上限額まで医療費を支払うと、4回目以降はさらに自己負担が下がります。
不妊治療のように回数が多い場合には大きなメリットです。
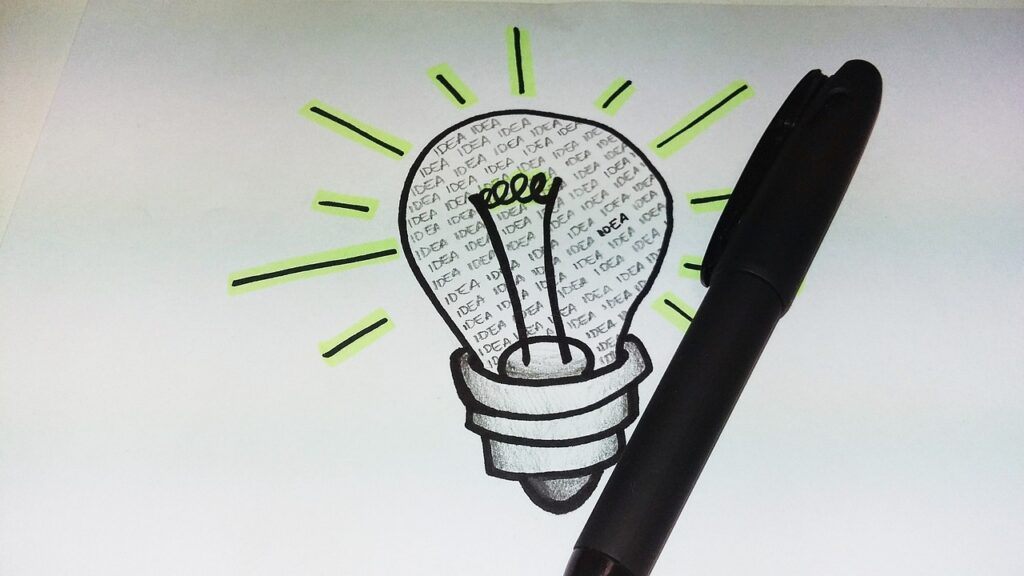
利用時の注意点
- 自由診療は対象外 → 最新オプション治療は適用外。ただし先進医療なら保険の特約でカバー可能。
- 自治体の助成と重複はできない → 助成分を差し引いた自己負担が対象。
- マイナンバーカード利用は対応状況に注意 → 病院によってはまだ限度額情報と連携できない場合あり。
まとめ|マイナンバーカードでさらに便利に!
不妊治療は経済的に負担が大きいですが、
- 国の保険適用
- 高額療養費制度
- 自治体の助成金
を組み合わせれば、実際の自己負担はかなり軽減されます。
さらに、マイナンバーカードを保険証として利用することで、限度額適用認定証の手続きが不要になるケースも増えているため、事前に登録しておくと便利です。
私たちも高額医療費制度を使用したときは、マイナンバーカードを保険証としていたため、限度額適用認定証の提示が不要になり手続きが楽ちんでした。マイナンバー保険証をお勧めします。
制度を正しく知って準備しておけば、「お金の不安」で治療を諦めずに済むはず。
これから不妊治療を検討する方は、ぜひ保険証のマイナンバー登録もあわせて確認してみてください。



コメント